相続の基礎知識
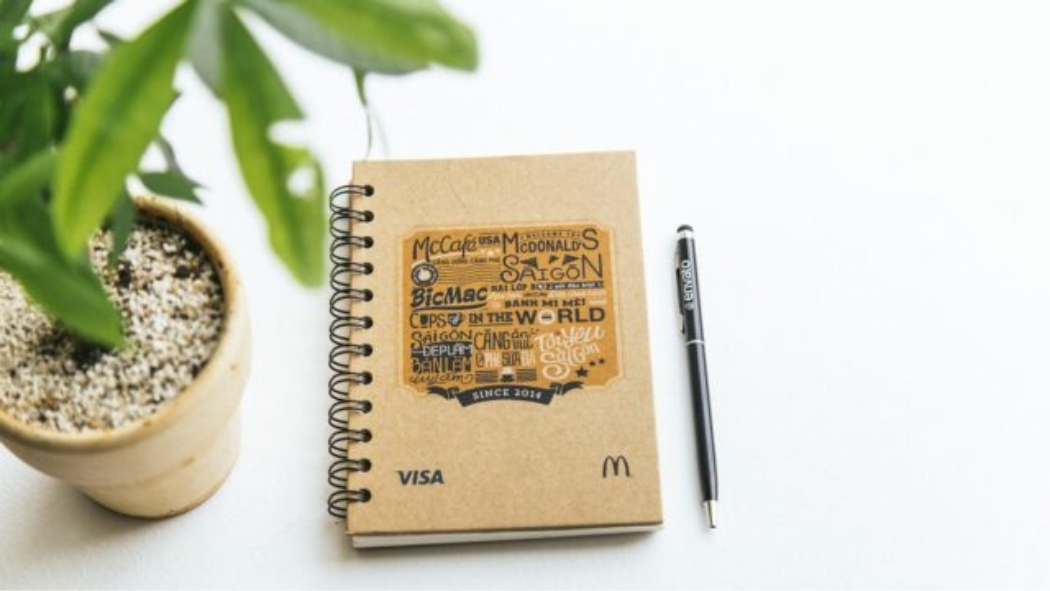
人が亡くなったとき、その人の財産は生きている人に引き継がれます。
これを相続といいます。
亡くなった人のことを「被相続人」といい、財産を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。
そして、相続される財産のことは、「遺産」や「相続財産」といいます。
相続人について
誰が相続人になるのかは、民法という法律で決まっています。
1.配偶者
被相続人に配偶者がいれば、常に相続人となります。
他に相続人がいる場合は、他の相続人と配偶者がともに相続人となり、相続財産を分け合って引き継ぐことになります。
2.子
被相続人に子がいる場合は、子が第一順位の相続人となります。
子が被相続人より先に亡くなっていた場合で、その人に子(被相続人の孫)がいれば、その人が代わりに相続人となります。
これを「代襲相続」といいます。
さらに孫も先に死んでいて曽孫が生きている場合も同様に代襲相続人となります。
3.親
被相続人が子や孫がいない場合(先に死んだ場合も含みます)で、被相続人の親が生きている場合は、親が第二順位の相続人となります。
親が先に死んでいた場合で祖父母や曽祖父母が生きていれば、その人が相続人となります。
4.兄弟姉妹
被相続人に子や孫、両親や祖父母等、第一順位の相続人も第二順位の相続人もいない(先に全員亡くなっている)場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっていて、その人に子(被相続人の甥姪)がいれば、その人が代襲相続人となります。
(なお、孫や曽孫のように、甥姪の子は代襲相続人にはなりません。)
相続分について
相続人が複数いる場合のそれぞれが相続する割合も民法で決まっています。
これを法定相続分といいます。
配偶者は、他の相続人と同時に相続人になりますので、その場合の法定相続分は、次のとおりです。
- 配偶者と子(孫等)が相続人の場合 1:1
- 配偶者と親(祖父母等)が相続人の場合 2:1
- 配偶者と兄弟姉妹(甥姪)が相続人の場合 3:1
なお、同一順位の相続人が複数いる場合は、その相続人の間で等分します。
ただし、相続分は、遺言や相続人同士の話し合い(遺産分割協議)により割合を変更することは可能ですし、誰か一人だけに全ての財産を相続させることも可能です。
そのため、法定相続分は、遺言がなく、相続人同士の話し合いが成立しない場合に適用されます。
遺産分割協議
相続人同士で、具体的に誰がどの遺産を取得するかを決めるのは、基本的には話し合いです。
この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
話し合いが成立した場合は、遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名押印するなどして、話し合いの結果を記録に残します。
この遺産分割協議書は、後に各種相続手続きのために使用しますので、必ず作成してください。
また、どうしても話し合いが成立しない場合は、家庭裁判所に申し立てて、遺産分割調停や遺産分割審判をすることもできます。
これは、裁判所の関与の下で遺産の分け方を決める方法です。
この場合、遺産分割協議書ではなく、裁判所が作成した調停調書や審判書が、遺産分割の結果を証明する書類となり、これがあれば相続手続きをすることができます。
相続財産について
被相続人の財産は基本的に全て相続の対象となります。
財産の中には、財産的価値のあるプラスの財産(不動産や預貯金等)だけでなく、マイナスの財産(借金等の債務)も含まれます。
ただし、被相続人の一身専属の権利(年金請求権や生活保護受給権など)などは、相続の対象にはなりません。
相続放棄について
相続人になると、マイナスの財産も全て相続することになりますし、プラスの財産だけであっても「関りを持ちたくない」「(不動産などは)管理するのが負担」等の理由で相続を望まないこともあります。
そういう場合は、相続放棄をすることで、最初から相続人にならなかったことになります。
相続放棄は、ただ「相続放棄する」と宣言したりそれを書面に残すだけでは足りず、必ず、家庭裁判所において「相続放棄の申述」という手続をとらなければなりません。
家庭裁判所で正式な相続放棄の手続をしていなければ、後に債権者から相続債務を請求された場合に支払う義務が残るので、注意が必要です。
また、いつでも相続放棄ができるわけではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければなりません。
また、相続財産の一部を処分したり消費したりすると、それ以後は放棄できなくなります。
相続登記 »

