遺産分割協議書
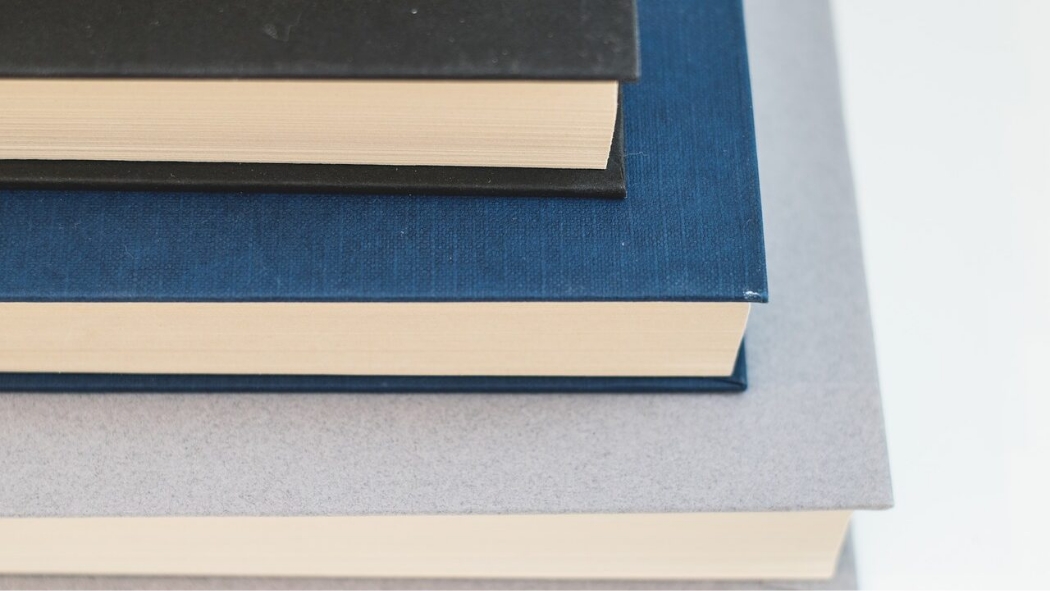
相続人が複数存在する場合、相続人同士で遺産分割協議が必要です。
その遺産分割協議の結果を書面化したものを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書の様式については、特に法律で決まっていませんが、適法に遺産分割協議が行われたことが証明でき、かつ、各種相続手続きで利用できるようになっていなければ、作り直しになったり、後で紛争が蒸し返されたりする危険があります。
遺産分割協議書にどのようなことを書くかというと、
- 被相続人の特定
- 遺産分割の内容
- 作成日付
- 相続人全員の署名押印
という形で作られることが一般的です。
被相続人の特定
被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日、死亡年月日等で特定します。
氏名以外の情報については、必ずしも全てを記載しなければならないというわけではありませんが、氏名以外に何も書かないと同姓同名の誰の相続なのか特定できません。
遺産分割の内容
どの相続人がどの財産を取得するのか、特定できるように記載します。
不動産については登記情報に沿った内容、預金であれば銀行名・口座種別・口座番号等を正確に記載します。
遺産に漏れがあると、記載されなかった財産を誰が取得するかが確定せず、その財産に関する相続手続きはできません。
その場合、改めてその財産に関する遺産分割協議をしなければならないので注意が必要です。
相続財産を調査しても判明しなかった財産が後から出てきたときの分配方法についても予め決めておくこともあります。
作成日付
遺産分割協議書の作成日付も書いておきます。
いつの時点を作成日とするかについて明確な決まりはありませんが、全員が一堂に会して署名する場合はその日、持ち回りで署名する場合は、最初の人か最後の人が署名する日を作成日として記入することが一般的です。
相続人全員の署名押印
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ無効となりますので、全員が参加したうえで決定したことを証明するためにも、必ず全員が署名押印します。
認印であっても一応効力はあるのですが、不動産登記や銀行の預金解約等、どの相続手続きでも実印の押印と印鑑証明書が求められることが一般的ですので、全員実印で押印するとよいでしょう。
遺産分割協議書の作成通数
遺産分割協議書は、全員が署名押印した1通があれば、その1通を使って全ての相続手続をすることができます。
しかし、遺産分割協議書は、当事者間で成立した合意内容を互いに証拠として持っておくという意味もあります。
そのため、相続人の人数分作成し、そのすべてに全員が署名押印して各自1通ずつ保管しておくことが一般的です。
« 相続登記

